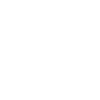春ですね。
というなんだか気の乗らない出だしなのは、私が北海道出身のくせして現在はだいぶ南に下ったところに住んでおるからに違いありません。私が生まれて育った場所というのは、道内でも有数の豪雪地な上、真冬はマイナス10℃を超えることもしばしば。数年前には、一晩で194センチ降って自衛隊出動……などというニュースで変に有名になりました。母が妹の高校入学式に出かけて吹雪に会う世界です。桜はゴールデンウィークを過ぎてから、葉っぱと一緒に咲くのです。
というわけで、自分の周りは暖かいのに、キンとした空気が懐かしく、雪で気分が盛り上がる私は生粋の道産子です。生粋も生粋、実のところ、私の先祖は開拓時代から北海道に生息しております。子どものころから聞かされたオソロシイ話の数々は、私たちに教訓をたたきこみました。曰く
自然をなめるなよ。
これに尽きます。
「あそこのオヤジさあ、飲みに出かけて帰ってきて、玄関先で鍵落としたらしいんだよね。朝起きて家族が玄関明けたら、そこで寝込んで凍死してたってさ」「あそこの息子、1月の夜に出かけたっきり帰ってこなくて、春になったら畑の真ん中からとけて出てきたんだよね」
とけて出てきたってあなた、そんなアイスの当たり棒みたいなこと言われても……。でも、本当なんです。小学校の頃は、「屋根の下を歩くな」と厳しく言われました。傾斜した屋根から、不意に雪崩のように雪が落ち、埋まって死ぬ事故が多かったからです。排雪(道路の雪をダンプに積んで別な場所に捨てにいく作業)用のロータリー除雪車に巻き込まれたり、ダンプにはねられる事故も多い時代でした。学校の帰りに吹雪にあうこともしょっちゅうです。自分の手をまっすぐ前に伸ばしたときに、掌が見えないほど視界の悪い吹雪の中を、平気で歩いて帰ってきていました。
ただし、鼻水が凍る世界を体験した人間にとって、マイナス50度、60度を記録したユーコン川流域、アラスカなんて、恐怖の世界です。この"To Build A Fire"(Jack London 1876-1916)『火を熾す』は、そんな世界に一人でふらふら出かけちゃった男の物語です。森の下見なんて、夏にしなよ……。もう読み始めから、「こいつ……なめてるな」と思わせる人です。だって、お弁当が一回分ですよ?!信じられない。濡れた時用の替えの靴下も持ってません。しかも頬がむき出し。繰り返します。息を吸い込んだ瞬間に、ピキピキって鼻の穴の中が凍るんです。そこを犬一匹連れて、古参の人の忠告も聞かずにひょいと出てきたんです。
アホです。
あらすじを紹介っていったって、始まった瞬間に、「あ~~、この人うろついて凍死するんだな」って想像がついて、ただそれだけです。でも私が紹介したいのは、あらすじではありません。つまり、先が見えているものをいかに最後まで読ませるか、という作家の腕に私は感服したわけです。
冷静に(と本人は思っている状態で)、こんな凍てついた世界を、男は息子の待つ家に向かって歩きます。脅威が見えないうちは、男は落ち着いています。忠告してきた人のことを、「ちょっと気が小さすぎるんじゃないか」なんて考えています。
そんな中、文字通り落とし穴に落ち込むのは一瞬です。こんな温度でも凍らない湧き水があって、その上に雪がふんわりかかっていて。そこに足を突っ込んでしまえば、引き抜いた瞬間に凍ります。即座に火を起こさなければ死ぬ。という極限状況の中、一度目はきちんと休憩して靴下を乾かすのですが、二度目はそうはいきません。木の梢が突き出ている下で火を起こします。
But before he could cut the strings, it happened. It was his own fault or, rather, his mistake. He should not have built the fire under the spruce tree. He should have built it in the open. But it had been easier to pull the twigs from the brush and drop them directly on the fire. Now the tree under which he had done this carried a weight of snow on its boughs. No wind had blown for weeks, and each bough was fully freighted. Each time he had pulled a twig he had communicated a slight agitation to the tree--an imperceptible agitation, so far as he was concerned, but an agitation sufficient to bring about the disaster. High up in the tree one bough capsized its load of snow. This fell on the boughs beneath, capsizing them. This process continued, spreading out and involving the whole tree. It grew like an avalanche, and it descended without warning upon the man and the fire, and the fire was blotted out! Where it had burned was a mantle of fresh and disordered snow.
まず、「それは起こった」という結末を読者に見せてしまう。「この人、まあちょっとやらかしたんだな……失敗だったね」といった説明が先に書かれる。それから木の動きが広がり、「来るぞ来るぞ……」という描写があって、最後に「あ~、やっちゃった……」という感覚と、「一巻の終わり」という絶望の一瞬が交錯する。という書き方がうまいなあ、なんて思うわけです。
時に愚かなことをする人間を、第三者の立場で見ていれば安心かというと、そうは限りません。予測していながら自分には何もできない時の方が、もどかしくやりきれないことだってあります。何がどうあろうとこの男を助けるものは無く、犬はこの男の結末を見届けたあと、一匹で暖かい火と食べ物のある場所へと去っていきます。
結末がわかっているからこそ、この小説は大きな余韻を残します。この男自身が父親であることも象徴的です。息子のことを思い出しながら、すこしずつ動けなくなっていく男を読んでいると、否応なく読者がこの男の父親(あるいは神と考える人もいるかもしれませんが)を見守る立場に移行せずにいられない。客観的に「もうだめだ」とわかっているからこそ最後まで読まずにいられないという感覚を持たされます。読者を含めた人間なんぞの思惑を屁とも思わない寒さが、深々(しんしん)と男を侵食していく経過を冷静に描き切り、物語は収束していきます。予測しうる結末に向かって歩いていくのに、しっかりと読まずにいられないのは、やはりこれが私自身を含めた小さな人間の、愚かな真実を突いているからなのでしょうね。
自然をなめてはアカンのです。


 English
English 日本語
日本語 中文(简体)
中文(简体) 中文(繁體)
中文(繁體) 한국어
한국어 Italiano
Italiano español
español Deutsch
Deutsch Русский
Русский